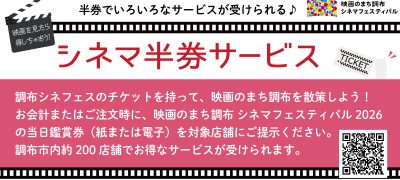<ちょうふアートサポーターズが聞く!>映画のまち調布 シネマフェスティバル 実行委員長 佐伯知紀さんへのインタビュー

2025.11.30
文化会館たづくりのとある会議室…
ちょうふアートサポーターズ(CAS)の3名が
映画のまち調布 シネマフェスティバル実行委員長 佐伯知紀さん
に気になることを聞いてみました!
Q1. どのような経緯で映画のお仕事をされるようになったのですか?
A.もともと早稲田の文学部に通うごく普通の文学好き、映画好きの学生でした。
専攻を決めるときには、日本文学(中世文学)にするかどうか迷っていましたね。ちょうどそのころに、別冊のかたちで発行された「日本映画史」(キネマ旬報)に強く刺激されて、執筆者が演劇科の先生方だったこともあり、同科に進みました。
その後大学院(文学研究科)に進み、修了後は東京国立近代美術館フィルムセンターに入職し、日本映画史を専門とする研究員・アーキビストとして映画フィルムの収集、保存、修復、公開に携わりました。フィルムセンター時代は、フィルムが現存しない“幻の映画”の発見、復元、上映にも携わりました。
たとえば…
>時代劇の巨匠 伊藤大輔監督の『忠次旅日記』(1927年)
>内容が一部欠落していた溝口健二監督の『瀧の白糸』(1933年)、
>ロシア連邦に残された戦前期日本映画(「満州映画協会」が在留邦人のために満州で配給)の現地調査で見つけた、国内には残されていない場面がある黒澤明監督のデビュー作、『姿三四郎』(1943年)
…は特に大きな仕事でした。
Q2. 一番最初に映画に興味を持ったのはいつですか? きっかけになった作品は何ですか?
A.松山にいた高校生のときです。映像美に惹かれました。
当時は1960年代の終わりから70年代初頭、きっかけになったのは『緋牡丹博徒シリーズ』などの加藤泰監督の東映任侠映画(ヤクザ映画)でした。いわゆるジャンル映画ですね。
東映は時代劇から任侠映画へと方向性を変えつつあった時期です。とはいえ、ヤクザ映画は大正・昭和初期を舞台にした時代劇なので、そこに様式美を感じました。とくに加藤泰の映画は、画面のひとつひとつがとても美しく、その感動が映画への入り口でした。つけくわえておくと、その加藤監督の師が先に触れた伊藤大輔監督なのです。
そして、決定的なきっかけになった作品は、溝口健二監督の『西鶴一代女』(1952年)です。ラスト・シーン、巡礼姿の田中絹代を見たときには震えました。
映画は「芸術」だと思いましたね。フランスのヌーベルバーグに影響を与えたのも分かります。わたしは溝口健二は今でも、日本映画の頂点だと思っています。この作品を見なかったら、この道は選ばなかったでしょう。
Q3. フィルムセンターでの映画研究者から、どのようなお仕事をされるようになりましたか?
A.思い出話になりますが…
今から23年前、2002年(平成14)に日本映画は対外国映画に対する比率(興行収入)で、30%を切りました。要するに公開された映画の収入の70%が外国映画(ほとんどアメリカ映画)によるもので、国産映画の衰退ぶりが明らかになったのです。歴代の最低値です。これを放置しておくと、儲からない日本映画は作らない、ヒットが見込まれる外国映画ばかりになってしまう。製作することで、各パートの技術者が育つ、現場で経験を積みながら養成されて、次世代が育っていくという回路が閉ざされてしまう。大げさにいえば、わが国映画産業の危機でした。そのことに危機感を持った国と映画界が協力して、2003年から映画振興政策に乗り出しました。
そのタイミングで美術館の学芸員から文化庁の芸術文化調査官(芸術文化課)に異動し、映画振興政策に携わるようになりました。映画研究者というよりは、行政の文化政策の中で映画・映像分野をどのように位置づけ、支援していくのか、そのための事業を立案し進めていくのか、という視点で様々な事業に関わってきました。
その仕事を通じて、映画・映像業界でたくさんの人と知り合い、繋がりができました。わたしは映画研究者であり、同時に映画・映像分野を応援する行政マンだった、結果的にそうなりますね。
Q4. 好きなことをお仕事にするのは難しいことだと思います。お仕事としてずっと映画に携わってこられた秘訣は何ですか?
A.運が良かったというのもありますよ。
映画好きであったこと、映画の学芸員・アーキビストの職に就いたこともありますが、振り返ってみると文化庁で行政職に就いて、政策課題(このときは映画振興)に対応していく、研究者とは異なる立場で、分野全体を見ながら進めていく仕事も面白く、なによりも自分の視野が広がりました。
Q5. 「映画のまち調布賞」は今回第8回目になりますが、どのような経緯ではじまったのでしょうか?
A.もともと、映画祭を企画する段階で「つくり手にスポットをあてる」というテーマがありました。
それはやはり、調布には角川大映、日活調布撮影所、現像所(東映ラボテック・東京現像所)、高津装飾美術など製作関連の会社があるということが大きかったですね。
映画関連の会社が集まっているということは、それだけ多くの関係者が日々調布に出入りしているということです。云ってみれば、撮影所は「工場」なのです。調布で映画の賞を作るんだったら、そういう人たちに寄り添った賞を作ろうということになりました。
わたしは、そこが「映画のまち調布賞」の大変ユニークなところだと思っています。監督賞・俳優賞とかはわかりやすいので、映画ファンが主体となっている地域の映画祭でもできますね。でも作品を支える現場のスタッフの顕彰は、やはり「映画のまち」調布しかできない。

Q6. 「映画のつくり手」にフォーカスするという部分が、この賞の大きな特徴なのですね。
A.技術部門の賞をつくるというのは、とてもハードルが高いことです。
「技術」の審査は、映画をよく見ている人や映画評論家であっても難しいものです。日本アカデミー賞、毎日映画コンクールなどの総合的な映画賞には技術部門がありますが、本格的なものは日本映画テレビ技術協会の賞、あとは職能団体が内部でそれぞれ賞を出しているくらいです。
「映画のまち調布賞」技術部門各賞(撮影賞、照明賞、録音賞、美術賞、編集賞)は、映画製作において実績のある技術者から構成された選考委員で討議の上での決定です。が、それが可能なのは、その方たちが調布で仕事をしている、馴染みのある、親しみのある街だからこそです。それは、仕事の後の酒席を含めてです。
そしてなにより、強調しておきたいことは、審査される作品は調布の皆さんの人気投票で決まることです。映画は調布の誇るべき文化資源、文化資産、特産品です。この資産を地域で盛り上げていく、そのための賞なのです。その意味で、山崎貴監督(白組)の「ゴジラ―1.0。」の米国アカデミー賞(視覚効果賞)受賞はとても誇らしい出来事でしたね。世界への発信ができました。
Q7.選考委員は市民が選ぶ対象作品に対してどんな感想をもっていますか?
A.結構いい反応をいただいています。「やっぱり調布の方は目が肥えているね」と。
Q8.今回の投票結果、受賞結果に対しての感想をお願いします。
A.良かったと思いますよ。
投票結果には、幅広い世代に親しまれる作品や一方でシリアスなものも入って。テレビドラマの劇場版もあり、バランスがすばらしいと思いました。
Q9.『国宝』が多くの賞を受賞していますね。
A.「照明」「録音」「編集」賞ですね。
これらの技術者の力も作品を支え、まれにみる大ヒットにつながったのだと思います。
Q10. 1年に見る映画は何本ですか?
A.100本超くらいです。できるだけ映画館に足を運び、どういう客層・年齢層が観客なのかも見ています。
Q11. 最近見た映画で良かった日本映画は何ですか?
A.「平場の月」「おーい 応為」「旅と日々」などです。今年は良い作品が多かったと思います。
Q12.最近の日本映画に感じられる変化はありますか?
A.映画自体というよりも、映画の見せ方が変わりましたね。
昔は松竹なら松竹系の劇場、丸の内松竹、新宿松竹、東宝なら日比谷東宝、新宿東宝、東映なら丸の内東映、新宿東映などのように全国に自社系列の劇場があり、それぞれが作った映画を上映して競争していました。松竹、東宝、東映と個性を競い合っていました。
ところが今はシネコンが当たり前になり、制作会社にかかわらず観客が入る映画を上映するようになった。だから観客が入る映画は上映回数がものすごく増えて、逆に入らなかったら徐々に回数が減らされてあっという間に終わってしまう。
劇場サイドもお客さん商売ですから、人気の高い作品を提供することは決して悪いことではなく、必然なんですが、その差がすごく極端になった。これが一番の変化です。見せ方、見られ方の構造が変わってしまった。回数を減らされる映画にも、実は優れた作品があるので、そこが残念です。
Q15.今後のシネフェスに対する期待は。
A.一番の期待は、調布で撮影賞や照明賞とかの技術賞を受賞したら、それがその人のキャリアとして認められるようになり、賞歴として履歴に書き込めるようになることです。
パンフレットのプロフィールはもちろんですが、国が映画の技術者を顕彰しようとするときに、賞歴に「映画のまち調布賞」受賞と記載されていたら、分かりました、立派ですね!と認められる賞に持っていきたい(笑)
Q16.そのためには回数を重ねることでしょうか。
A.一回一回、最低、十回は続けないと、ただの思いつきになってしまう。継続こそが大切です。
同時に市民に支持され続けないといけない。こんなフェスティバルに私たちの税金を使っていいのですか?という市民に対して、続けることの意義を訴える必要があります。私の実感では、映画界の技術者たちにはこの賞の重み・信頼感が伝わってきはじめているので、これからも着実に重ねていきたいと思います。
それと、フェスティバルの継続のなかで映画作品だけではなく、南北ギャラリーの映画関連の資料展示も、注目度が増していて、図書館の映画資料室の役割も大きくなってきています。映画をつくるまちは、映画を残すまちでもあるのです。
Q17.近年は、配信作品もシネコンで上映されています。映画のかたちは今後も変わっていくのでしょうか?
A.映画はその時の一番新しい科学技術を取りこんで成長してきたと思います。
写真から映画(モーション・ピクチャー)、無声からトーキー(有声)、白黒からカラー、フィルムからデジタルに転換してきました、映画は最新の技術で物語(映像)を伝えるメディアなのです。そのような根本に返れば、最新の技術で映像の物語を紡ぎ、スクリーンに上映された瞬間にそれはもう映画です。かたちは変われど、その根本は変わりません。
Q18. 最後に、佐伯実行委員長が考える映画の魅力とは?
A.映画史の研究をずっとやってきて思うのですが、これほどその時代の価値観と空気を捉えているメディアはありません。
戦前の日本映画を見ると、世相は違えど当時の人々の暮らしの中の人間関係や家族関係が実は今の私たちのそれと通じており、その時代を生きていた人々の心の動きは今とさほど変わっていないことがはっきりとわかります。
映画はその時代を知ることができるメディアとして残っていく、そこが魅力だと思います。
フィルムからデジタルへと変化しましたが、人間が多くの人と一緒に映像のドラマを見て泣いたり笑ったりすることは決して終わらないと思いますよ。

PROFILE
佐伯 知紀 さいき とものり
映画のまち調布 シネマフェスティバル実行委員会 委員長。
1954年愛媛県生まれ。84年早稲田大学大学院文学研究科修了(修士)。
専門は日本映画史・映画映像政策論。
同年から東京国立近代美術館フィルムセンターに在籍、同主任研究官を経て、文化庁芸術文化調査官(映画・映像担当)。
フィルムセンター時代は、ロシア連邦に残された(「満州映画協会」所有)戦前期日本映画の所在調査・研究などに従事。
文化庁では映画振興政策の立案・実施に参画、主な担当事業に「ndjc:若手映画作家育成プロジェクト」(https://ndjc.bunka.go.jp/)
など。現在は特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)顧問、優秀外国映画輸入配給賞審査委員、公益財団法人川喜多記念映画文化財団理事。